なみなみ通信Vol.10

海況情報
今年の夏は猛暑の影響を受け、筑前海、豊前海では平年より2〜2.5℃高めで推移しました。
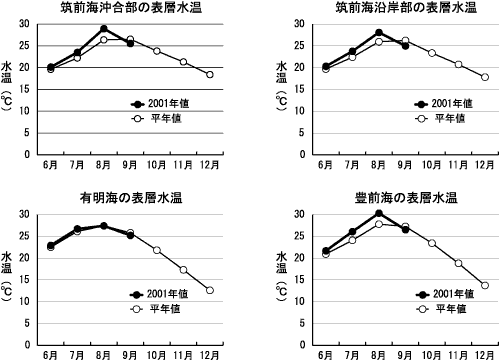
筑前海沖合海域
7〜8月の表層から10m層まで水温が平年より高くなっていました。20m以深では 平年並みしたが、対馬南方海域では過去70年の観測史上で最も高い30.0℃を記録しましたが、8月下旬には 解消しています。8月上旬から中旬までは沖縄から島根県沖まで30度を超える値が観測されています。 表層域の塩分は、低塩分傾向でした。
筑前海沿岸部
8月の福岡湾での水温は、平年値より2.2℃高く、塩分は平年並みでした。 湾奥部の底層では貧酸素状態が観測されましたが、魚介類のへい死は見られませんでした。8月下旬の波浪により、 テイサン遡上対は改善されました。
有明海
7月上・中旬は平年より0.7℃高めでしたが、7月下旬以降は平年なみで 推移しています。他海区でみられた高水温の状況は観測されませんでした。
豊前海
7月の表層水温は2℃、8月は2.5℃高めでした。7〜8月と高水温が継続した年は ありませんでしたが、9月にはほぼ平年並みになっています。
マダイ幼魚の資源
平成11,12年の調査では、非常に少ない状況でマダイ資源の減少が心配されましたが、 今年の調査では近年で最も資源水準の高かった平成7年以上に回復しています。 来年度は立子(1歳魚)の良好な漁獲が見込まれると思われます
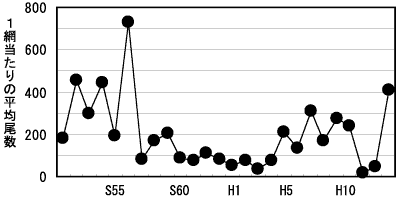
マダイ幼魚再捕尾数の経年変化
(研究部漁業資源課)
カタクチイワシの漁況
9月中旬の調査では、大きな魚群は観測されず所々に小さな反応があるのみです。 最も強い魚群反応が観測された唐津湾では、平均体長が24mmのカタクチイワシを16尾採捕しました。 日間成長率から計算すると漁獲対象となるのは、10月上旬以降と思われます。カタクチイワシの餌料となる プランクトン量は福岡湾、唐津湾とも少量で沖合域より沿岸部で比較的多い結果となりました。

(研究部漁業資源課)
豊前海の種苗放流結果
クルマエビ:計画どおり2回実施し、合計で391万尾放流することが出来ましたが、中間育成中にシャットネラ
による赤潮が6月中旬〜7月上旬並びに7月下旬〜9月上旬にかけて沿岸域で発生したため、計画通りの換水が出来ず
歩留りが若干低下しました。
ガザミ:北九州地区及び苅田町漁況は、中間育成を実施し3割以上の歩留りがありました。その他の地区は、
従来どおり直接放流しました。
ヨシエビ:飼育期間が短く、また搬入時の種苗が不揃いであったため、放流種苗の大きさにに多少バラツキが
あったものの飼育は良好で163万尾放流することが出来ました。なお、南部地区では直接放流しました。
豊前海での種苗放流結果

(豊前海研究所)
有明海のり生産の基本戦略
海況条件(栄養塩、水温、塩分)が順調に推移するなか、今漁期の採苗は10月4日から始まり、
芽付きも良好です。
本漁期の対応としては、ここ数年珪藻プランクトンの増殖時期が早くなっていることから、
今年は栄養塩の期待できる漁期前半の生産性を高めることが重要です。
①秋芽生産のあかぐされ病対策の集団管理を徹底する。
冷凍入庫までは網に適正な干出をかけてありますが、網の単張り後からは干出をとらない管理が目につきます。 秋芽生産は水温の高い時期だけにあかぐされ病は急激に蔓延しますので、漁場全体で適正な干出をかけるよう に心がけてください。
②冷凍網の出庫時期を出来るだけ早くする。
近年、冷凍生産期にノリの色落ちが早く起こる傾向にあります。生産性の高い時期を有効に使うために、 水温条件を勘案しつつ、冷凍網の出庫を出来るだけ早く設定することを考えています。

種付けの準備作業
(有明海研究所のり養殖課)
アサリ放流、サルボウ天然採苗中間結果
アサリ放流追跡調査
5月に柳川、大和、大牟田の各地先に保護区を設定し放流しました。放流直後から追跡調査を実施しています。 降雨による出水などの影響で、周辺域への拡散など分布にかたよりが見られました。8月の調査では生残率は 6割程度でした。法隆寺に平均殻長が2cmであったものが、9月下旬には平均殻長3cm程度に成長しています。サルボウの天然採苗
6月下旬に漁業者の協力を得て、干潟域の25ヶ所に採苗施設を設置しました。採苗器はヤシ繊維を取り付けた ノリ網で、地盤から約30cmの高さに固定して、サルボウ浮遊幼生を付着させました。幼生の着生は7月下旬から 始まり、8月下旬までに全ての採苗施設で順調に着生し、9月中旬には殻長7mmに成長しています。
サルボウ採苗施設の清掃作業
(有明海研究所資源増殖課、のり養殖課)