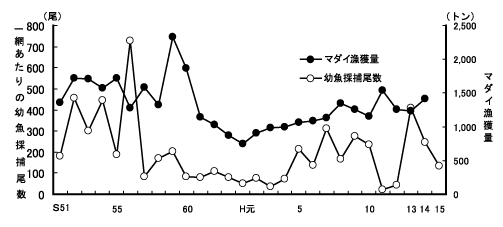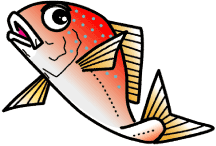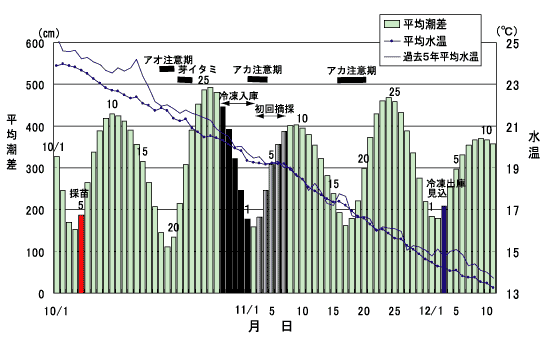側傒側傒捠怣Vol.18

奀嫷忣曬
丂奀悈壏偵偮偄偰丄拀慜奀嬫偼傎傏暯擭暲傒丄桳柧奀嬫丒朙慜奀嬫偼7乣8寧偵偼傗傗掅傔偱悇堏偟偰偄偨偺偑9寧偵偼暯擭暲傒偲側偭偰偄傑偡丅
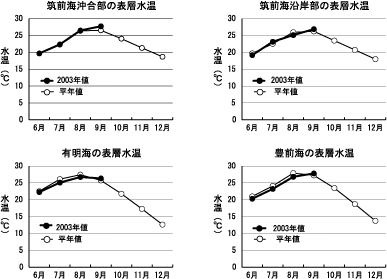
儅僟僀梒嫑帒尮挷嵏傪幚巤偟傑偟偨
丂亅慡挿13噋枹枮偺儅僟僀偺嵞曻棳悇恑傪両亅
暯惉15擭7寧11擔偼廆憸丒敂壆奀堟丄15擔偼搨捗榩奀堟偵偍偄偰1偦偆屷抭栐嫏慏偵傛傞儅僟僀梒嫑乮僕儍儈乯挷嵏傪峴偄傑偟偨丅偦偺寢壥傪偍抦傜偣偟傑偡丅丂
崱夞偺挷嵏偱偼丄僕儍儈偺嵦曔偼133旜乛栐偲尭彮偟偰偄傑偡偺偱丄慡挿13cm枹枮偺儅僟僀偵偮偄偰偼嵞曻棳傪悇恑偟偰偄偒傑偟傚偆丅傑偨丄杮擭偺摿挜偲偟偰偼丄僠僟僀偺梒嫑乮僠僐乯偑1栐偁偨傝123旜偲丄嶐擭偺16旜偲斾妑偟偰懡偔傒傜傟傑偟偨丅
暯惉11丒12擭偺杮挷嵏偱偼丄僕儍儈偺検偑嬌傔偰彮側偄寢壥偲側傝丄奀堟偺儅僟僀帒尮偺尭彮偑怱攝偝傟傑偟偨偑丄15擭嫏婜慜敿偺嫏柾條傪傒傞偲丄傗偼傝3丒4嵨嫑摍偺戝宆嫑偺嫏妉偑巚傢偟偔側偄傛偆偱偡丅
師偵丄13丒14擭偺挷嵏偱偼丄暯嬒擖栐悢偑夁嫀10擭娫偱嵟崅偩偭偨7擭偲摨摍埲忋偵夞暅偟偰偍傝丄15擭埲崀偺彫宆嫑偺帒尮偺憹壛偑尒崬傑傟傑偡丅
乮尋媶晹嫏嬈帒尮壽乯
丂
|
丂
暉壀榩偵偍偗傞僋儖儅僄價抰僄價偺昗幆曻棳
|
暉壀榩偺僋儖儅僄價偺昗幆曻棳偼丄榩撪偱偺堏摦丒惉挿側偳偺惗懺傗曻棳岠壥偺挷嵏偺偨傔丄庬昪曻棳偵崌傢偣偰峴傢傟偰偄傑偡丅偙偙3擭娫偼丄嫏妉僒僀僘偵憡摉偡傞懱挿栺10噋偺僋儖儅僄價偵儕儃儞傪憰拝偟偰曻棳偟丄偦偺堏摦傗惉挿傪柧傜偐偵偟偰偒傑偟偨丅 崱擭偼丄7寧偵戝妜抧嬫偐傜庬昪曻棳僒僀僘乮懱挿30噊乯偺抰僄價栺10枩旜偵旜巿僇僢僩昗幆傪偟偰曻棳偟傑偟偨丅偙偺昗幆偼丄偙傟傑偱偺嫏妉僒僀僘偵偟偐憰拝偱偒側偄儕儃儞偲堎側傝丄傛傝彫宆偺庬昪曻棳僒僀僘偺抰僄價偵傕昗幆壜擻側偨傔丄抰僄價抜奒偺堏摦忬嫷傪捛愓偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅偙偺僄價偺嵞曔偐傜摼傜傟偨寢壥傪惗懺傗曻棳岠壥夝柧偺偨傔偺帒椏偲偟丄僋儖儅僄價偺憹怋偺偨傔偵栶棫偰偰偄偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅 |
乮尋媶晹愺奀憹怋壽乯 |
暯惉15擭搙桳柧奀偺傝梴怋偺婎杮愴棯
嵦昪偼9寧24擔偺慻崌挿夛媍偱10寧5擔屵慜6帪弌峘偲寛掕偝傟傑偟偨丅10寧2擔尰嵼偺奀嫷偼丄悈壏偼24.2亷丄斾廳偼23.5丄塰梴墫乮DIN乯偼17.6兪gt乛l偲嵦昪擔偵岦偗偰丄椙岲側忬嫷偱偡丅
杮擭搙偺廐夎惗嶻婜偲椻搥惗嶻婜偵偮偄偰偺峫偊曽偼埲壓偺偲偍傝偱偡丅
| (1)廐夎惗嶻婜 | |
|
|
| (2)椻搥惗嶻婜 | |
|
|
|
朙慜奀偵偍偗傞嵧攟嫏嬈偺怴偨側庢傝慻傒乮僷乕僩嘦乯
朙慜奀偵偍偄偰偼丄僋儖儅僄價傪偼偠傔偲偡傞峛妅椶傪懳徾偵嵧攟嫏嬈傪愊嬌揑偵揥奐偟偰偄傑偡丅嵧攟嫏嬈偵娭偟偰偼丄嫏嬈幰傕偦偺昁梫惈傪廫暘擣幆偟丄尋媶強偲嫤椡偟偰峏側傞曻棳岠壥偺岦忋傪栚巜偟偰婃挘偭偰偄傑偡丅
僋儖儅僄價偵偮偄偰偼丄崱婜2抧嬫偱奺2夞偺拞娫堢惉傪峴偄傑偟偨丅嫏嬈幰偼偙偺婱廳側庬昪偺曻棳岠壥傪傛傝崅傔傞偨傔偵丄嶐擭棃幚巤偟偰偄傞乽奀掙曻棳乿曽幃偵壛偊偰丄崱婜俀夞師暘偐傜丄朙慜丒抸忋抧嬫偵偍偄偰塅搰嫏嫤惵憇擭晹偺敪埬偱丄曻棳庬昪偺堦晹傪梡偄偰乽埻偄栐曻棳乿曽幃偵傕庢傝慻傒傑偟偨丅
偙偺乽埻偄栐曽幃乿偼丄暯惉尦擭傑偱奺嫏嫤偺抧愭偱峴傢傟偰偄偨曽朄偱偡偑丄埲慜偲偼廂梕僒僀僘偑慡偔堎側傝丄崱夞偺応崌偼曻棳僒僀僘傑偱堦扷拞娫堢惉偟偨抰僄價傪梡偄丄揤慠奀堟傊偺撻抳傪栚揑偵峴偄傑偟偨丅
丂埻偄栐愝抲応強偼丄姳挭帪偱傕姳忋偑傜側偄僈僓儈偺拁梴巤愝偺堦晹乮栺400噓乯傪棙梡偟丄暯嬒懱挿37.2
mm偺拞娫堢惉抰僄價栺70,000旜傪梡偄偰8寧2擔偐傜幚巤偟傑偟偨丅
丂丂丂
丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
亂帞堢宱夁摍亃
埻偄栐偵傛傞抰僄價偺撻抳帞堢偱偼丄帞堢奐巒摉弶偐傜2擔屻傑偱偼丄懡偔偺屄懱偑愽嵒偡傞偙偲側偔奀掙偵惷巭偟偰偍傝丄塧傪梌偊傞偲塲偓側偑傜塧傪懆偊偰偄傑偟偨偑丄3擔傪宱夁偟偨崰偐傜嵒偵姰慡偵愽傝丄塧傪梌偊偰傕奀掙忋偱愛塧偡傞傛偆偵側傝傑偟偨丅抰僄價偼丄5擔娫偺帞堢偱暯嬒懱挿偑39mm乮暯嬒擔娫惉挿栺0.36mm乯傑偱惉挿偟丄偟偐傕廂梕帪偵偼60亾埲忋偺屄懱偵傒傜傟偨曕媟忈奞偑丄曻棳帪偵偼慡偔擣傔傜傟側偔側傝傑偟偨丅
崱夞偺埻偄栐帞堢偱偼丄帞堢婜娫偑揤岓偺搒崌偱5擔娫偲抁婜娫偱偟偨偑丄惉挿丆撻抳媦傃曕媟忈奞偺夞暅摍曻棳庬昪偺寬昪惈傪妉摼偡傞偆偊偱丄旕忢偵椙偄寢壥偑摼傜傟傑偟偨丅崱屻偼偝傜偵夵椙傪壛偊偰丄偙偺埻偄栐曽幃傪宲懕幚巤偟偰偄偔梊掕偱偡丅
乮朙慜奀尋媶強愺奀憹怋壽乯
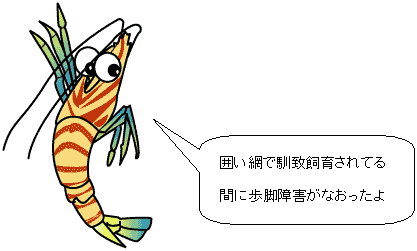

埻偄栐偺愝抲応強乮朙慜巗孊愳抧愭乯
丂
丂
丂